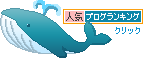月に一度、スターバックス弘前公園前店にて「みんなのこぎん」が開催されています。
私が刺しているのは、佐藤陽子先生の『津軽こぎん刺し図案集~高橋寛子 天からのおくりもの』の図案です。
少しずつ進めて、紋様ができてきたので、みなさんの作品とともにお伝えします。
スポンサーリンク
スターバックス弘前公園前店

旧第八師団長舎をリノベションしてオープンした、スターバックス弘前公園前です。
弘前市役所のすぐそばで、道を挟んだ向こう側は弘前公園のお濠端。
斉藤美佳子さんが主宰の「みんなのこぎん」は、半年前まで「スタバdeこぎん」の名前でした。
飲物は各自持ちですが、月会費はありません。
美佳子さんが善意 で始められたこぎん刺しの会なのです。
こぎんのベンチがあって、とっても落ち着いた店内。
窓から植え込みの木々が見えて、陽射しが明るく射します。
みんなのこぎん

久しぶりにreiさんがお見えになって、こぎん刺しやパソコンのことを教えてくれました。
reiさんは、gardengardenを運営されるハンドメイド作家。
プログラミングも得意な方です。
パソコンを購入するときは、「CPUもチェックしたらいいよ」と教えてくれたのは、reiさんでした。
さて、リンゴのモドコはコングレスと糸の組み合わせで、幾通りも楽しめます。
いまの季節、リンゴ園は赤く色づいているので、こぎん刺しのリンゴはまさにタイムリー♪

美佳子さんが見せて下さったのは、雪の結晶をモチーフにしたこぎん刺し。
フレームに入れると、虹色の色が映えますね。
色糸やコングレス生地は現在、草木染めや虹色などがあって、多種多様。
でも、元来は麻布を天然藍で染め、白い木綿糸を用いました。
こぎん刺し今昔
江戸時代の文献にも登場する、こぎん衣は農家が自家栽培の麻を自ら織り上げた布を着物にしたのです。
すべて手織りの麻布ですから、農民は生涯において数少ない衣を大切に着続けました。
その歴史をひもといた田中忠三郎先生のBOROは、オーストラリアの展示でも好評だったとか。
麻の古布を展示していたアミューズミュージアムは惜しまれながら、閉館。
こぎん衣は農民の哀史と、草の根のように強い魂の証だと私は感じています。
佐藤陽子こぎん展示館
「こぎんのいま 伝統を未来へ」というテーマの連載。
高橋寛子さんの図案を陽子先生が、目を凝らして見つめる写真が印象的です。
陽子先生の師であった高橋寛子さん。
15歳から現・弘前こぎん研究所に勤め、後に夫となった高橋一智氏とこぎんの再興に務めました。
陽子先生の師を思う心遣いが、図案集を開くたびに胸に沁みます。
「この素晴らしい模様をもっともっと刺してもらいたい。その気持ちだけです」と、東奥日報に陽子先生の言葉がありました。

私がいま刺しているのは、陽子先生が刊行した「津軽こぎん刺し図案集」の文様です。
コーヒーカップを置いている辺が、刺し始め。
まだまだ完成には遠く少しずつ刺していました、図案と布目を確かめながら。
文様を津軽弁で「モドコ」といいます。
かつての農家の女性たちは、頭の中で文様を組み立て刺し綴りました。
紙も筆記用具も、彼女たちには高価すぎて手が届かなかった。
それにしても、すごい手仕事の技!
モノは乏しくても、自分の能力を惜しみなく働かせたのでしょう。
まとめ
みんなのこぎんに参加して、こぎん刺しを楽しんでいます。
佐藤陽子先生が掲載された東奥日報10月4日の「こぎんのいま」シリーズ、とっても胸に沁みて、色とりどりの糸や布に恵まれている幸せを噛みしめています。
スポンサーリンク