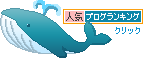「津軽の美~武士の工芸、庶民の民芸」と題された企画展は、津軽家のお雛道具や印章から農民の生活道具やこぎん衣など多数、展示。
そして今回は写真撮影OKのブースがたくさんありました。
弘前市が誕生して130年の記念に開催の企画展は、とっても見応えがあるので紹介します。
スポンサーリンク
津軽家の宝物

武士の工芸といえば、何といっても日本刀ですね。
弘前には歴代藩主の日本刀が何振りも、きちんと保管されています。
写真にあるのは、渋江抽斎(しぶえちゅうさい)の脇差と江手描き文散らし刀架。
江戸時代の津軽塗り は手描きもあったのですね。
刀匠が弘前市に隣接する田舎館村に在住して、イベント時には日本刀を解説してくれます。
中畑さんは若い頃から刀作り一筋の刀匠です。
日本刀は平安時代末期には完成され、製法は変わらないそうです。
すごいですね。
あでやかな雛道具

お姫様が輿入れするとき縁起物として、貝合わせや貝桶のお道具とともに長い行列をなしたことでしょう。

細やかな細工がしてある雛道具は、あでやかで見応えがありました。
津軽家旧蔵の雛道具。
御道具類がこれほどそろっているのは珍しいそうです。
このほか歴代藩主の印章などもありました。
弘前は、弘前藩の藩日記が今も弘前市立図書館にありますし、第一級の資料がそろっていることを改めて感じます。
江戸から明治に移行するとき、混乱期に燃やしたり戦乱に巻き込まれたりした藩があったことを考えると、弘前は欠けることなくきちんと保管。
スポンサーリンク
民芸の美

写真は農民の雨具、伊達ケラです。
『武士の工芸』の向かい側の展示室に移動すると、そこは農民が自ら手作りした生活道具がたくさんあって、質実な美に圧倒されます。
すね当てはハバキともいうのですね。
模様が織り込まれて、きれいでした。
伊達ケラは、蓑(みの)なのですが、津軽では美しい模様を織り込み、新婦への贈り物としたそうです。
津軽だけにある装飾性が高い蓑で、これも珍しい。
さて新婦は新郎へ、こぎん刺し衣をプレゼント。
までいな刺しこぎん

麻布にびっしりと刺し模様。
下半分の藍色のところも横刺しをほどこしていますよ。
制作にどれほどかかったのだろう?
非常に手が込んでいますね。
「までい」です。
津軽弁の「までい」は、丁寧という意味。

庶民の民芸ということで、南部菱刺しも展示。
左側の前垂れは古いものなのでしょう。
見るからに年代ものでした。

筒描きの手描きもありました。
夜着(よぎ)として作られたのです。
家紋入り。
円錐形の筒に入れた糊で絵を描く技法です。
弘前市の個人所有。
プリントや機械染めでは出ない、味わい深い染色法です。

『津軽の美 武士の工芸 庶民の民芸』企画展は6月2日まで。
新緑が映える弘前市立博物館の建物は、モダニズム建築の巨匠・前川國男が手がけました。
昭和52年に開館。
館内の窓から眺めることができる弘前公園のロケーションもすばらしい。
まとめ
庶民の民芸に展示されていた伊達ケラやブドウ蔓のカゴなど、とても保管状態が良く、こぎん衣も見事。
もちろん津軽家のお雛道具はあでやかで、ためいきの嵐です。
前川國男が手がけた建物で津軽の宝を見学できるって、すごいですね。
スポンサーリンク